![]()
![]() (認知症を支える家族の会)
(認知症を支える家族の会)![]()

*木々の柔らかな若葉がまぶしく輝き、爽やかに風も吹いています。
緑の季節がやって来ました。
皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか?
*5月の活動は6日(火)の交流会、9日(金)の運営委員会、16日(金)
のコーヒーポット、23日(金)の会報印刷になります。
◎介護についてのお悩みやご相談を語り合う交流会は、事前の申し込みは
不要です。
ご参加ご希望の方は、5月6日(火)直接会場の福祉センター(鎌倉市
御成町)にお越しください。
5月 6日(火) 交 流 会 13:30〜15:30
5月 9日(金) 運営委員会 10:00〜12:00
5月16日(金) コーヒーポット14:00〜15:30
5月23日(金) 会報印刷 9:00〜12:00
6月 3日(火) 交 流 会 13:30〜15:30
6月13日(金) 運営委員会 10:00〜12:00
6月20日(金) コーヒーポット14:00〜15:30
6月27日(金) 会報印刷 9:00〜12:00
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
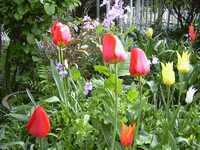
現在、2本杖歩行の生活を余儀なくされている。休み休み時間を掛ければ、社会的な活動に支障はない。ただ、移動の環境が “こんなだったらいいなぁ”と、感じたままを書いてみた。
まずは、道路である。歩道がひろいのは、いい。鎌倉のような道路事情では難しいことは承知のうえーのはなし。そして、歩道には“ベンチ”。通院の際に利用する「鎌倉芸術館通り」は、樹木のわきにチョットした座る場所があり、よく利用している。ベンチについて、もうちょっと話を。福島県会津の七日町通りの例。各店先に人ひとり座れる椅子が備えられている。商品の配列の工夫で座れる場所が確保されており、こういったやさしさの感じられる商店街、すてきだなぁ。
よく出かける本屋さんがある。長時間立って本を選ぶのは辛い。以前は、店内に2、3脚のイスが備えられていた。運よく座ることができるとラッキーだが、空いてるイスに荷物なんぞを置かれているのに遭遇すると“この野郎、座れないだろう”などという気持ちになる。最近行ったらイスは、片付けられていた。残念!
昨年11月、上野の東京国立博物館で開かれていた「はにわ展」を見に出かけた。上野東京ラインで乗り換えなしに行けるのは、いいな。館内は、家人があらかじめ博物館に頼んでおいた車イスで見学。朝早いにもかかわらず、入館者はそれなりに多かった。
「どうぞ、前のほうにー」みんな、やさしかった。「はにわ」は、人の心をホッコリさせるのかもしれない。みんな“やさしい”じゃないか。いやな顔など感じなかった。いい気持ちで鎌倉に戻ることができた。
認知症の人にやさしいまちーそれは、誰にでもやさしいまちを創ることです。
どうしたら「誰にでもやさしいまち」は具体化できるのでしょうか。
鎌倉市の第9期高齢者保健福祉計画には、基本方針に「認知症の人を支える体制づくり」が加わっています。そして、主要施策として
①認知症への理解の促進
②認知症本人とその家族への支援の充実
の2点があげられています。「認知症への理解の促進」特に大事な点かなぁーと思っています。これは、「認知症」に限ったことではないのでしょう。みんないろいろな生活課題を抱えています。ごく、小さなことかもしれませんが、身近なことから、「気配り・目配り・心配り」に心がけたいと思っています。
混雑しているなかで、お互い譲り合うーそんな社会が「共生社会」創造の第一歩になるのでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

4月17日(木)かまくらりんどうの会の総会が行われましたのでご報告申し上げます。10時、向山副代表による司会で始まり、渡邊代表の挨拶の中で、今日の記念講演で紹介する“地域包括支援センター”は「これからの福祉を考える上で非常に大事な役割をしていくものであろう」とお話がありました。
その記念講演は総会に先だって行われ、地域包括支援センター 鎌倉きしろ管理者 村瀬磨美氏を講師としてお迎えし「認知症の方と家族のふつうの暮らしの幸せが続くために 〜地域包括支援センターでの活動報告〜 」という演題でプロジェクターや広報誌を使い、ご自身の経験談や活動を画像や写真を交えてお話していただきました。
村瀬氏所属の「鎌倉きしろ」(大町・材木座を担当)では、ケアしている人たちの交流の場「ケアラーズカフェ@お庭」を定期的に開催したり、誰もが立ち寄れる「お庭カフェ」を開放しているそうです。
地域包括支援センターは市内に10カ所あり、担当する地域がそれぞれ決まっています。
認知症に関してはいくつかの事例を挙げ、“認知機能の低下が見られた時には、情報収集して何がその方の気持ちに影響しているかを考え環境を整えることが大切”と仰っていました。地域包括支援センターは高齢者だけではなく、あらゆる世代の相談も受け付ています。その方達への必要なサポートにつなぐ役割も担っているということでした。
休憩後の11時過ぎ議事に入りました。前年度活動報告、会計報告、今年度活動案、予算案について各担当者から報告、最後に運営委員の紹介がありました。それぞれ皆様から了承の拍手をいただき、総会は滞りなく終了となりました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
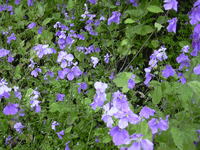
花冷えの中、4月1日の交流会に地域包括支援センター職員、認知症看護認定看護師、会員、合計10人が集いました。定例の唱歌を歌い、自己紹介後介護に困っていること等を話しあいました。
同じことを何度も話す、物をあちこち移動し探すのが大変、入所中のご本人より頻回に電話がかかり追い詰められた気持ち等々。病気なのだからと理解しているつもりでも介護者の気持ちは辛く、どうしたらよいのだろうというご相談がありました。加えて普段介護に携わっていない家人からは、なかなか現状を理解されず、いらだちを覚えるというお話もありました。会員それぞれに思い当たる経験や気持ちであり、心に響くお話ばかりでした。
ある会員より「自分も日々の暮らしの中で老いや病気、不安や寂しさを感じており、ご本人のお気持ちが手にとるようにわかり、ひとごととは思えない。」と発言があり、ご本人、介護者という壁が一挙になくなり自分事として感じられた会員も多かったようです。
専門職の方から辛さ、大変さへの労いや介護のための試行錯誤への共感と介護者の認知症の方々へのそれぞれの真剣な向き合い方に感銘を受けたというご意見をいただきました。介護の悪戦苦闘にはそれぞれの方の丸ごとの人間が出ると出席者が深く思い至ったことでした。 mm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「五月(さつき)」とは旧暦の呼び方で、6月に相当します。旧暦の5月…つまり現在の6月は梅雨の時期に当たることから、元々「五月晴れ」は、日本の気候の特徴である「梅雨の晴れ間」や「梅雨の合間の晴天」を指しました。梅雨の長雨で、空模様も人々の気分もいまいち優れない期間に、ふと晴れ間が見えたときに使う言葉です。新暦5月のカラッとした晴天とは異なり、暑い夏の訪れを予感させる晴れのことだったのです。
俳句の季語では、梅雨明け直後の晴れ間も「五月晴れ」と呼ぶことから、初夏の季語として使われています。ところが時が経つにつれて、五月晴れの使われ方は変化してきました。言葉の響きから、誤って「新暦の5月のよく晴れた日」という意味でも用いられるようになり、この誤用も正しい意味の1つとして定着しました。
そのため五月晴れについては、主な国語辞書でも、「五月雨の晴れ間、梅雨の晴れ間」という本来の意味と、「5月のさわやかに晴れ渡った空」という新しく加わった意味の両方が記述されています。なかなかややこしいですが、同じ年中行事でも、地域によってはその行事を旧暦で行うところもあれば、新暦で行うところもあり、一律に言葉の意味を統一するのは難しいようです。
五月晴れの空に映える鯉のぼり、残念ながらあまり見られないようになりましたね。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

八十八夜の別れ霜と申します。これからますます気候もよくなってきますね。先日総会が開かれました。今年度も役員一同それぞれにできる範囲でがんばりたいと思います。ご要望、質問、ご意見や原稿をお待ちしています。木々の芽吹くこの時季は体調を崩しやすいそうです。どうぞご自愛くださいませ。a.y
☆会報へのご意見、ご要望は下記の発行者、編集担当までお知らせ下さい。
発行者:かまくらりんどうの会 代 表:渡邊武二 TEL45-6307
編集・印刷:菅井TEL46-5369 山際 TEL24-8765